【事例9選】社内コミュニケーションを活性化させるイベントの紹介
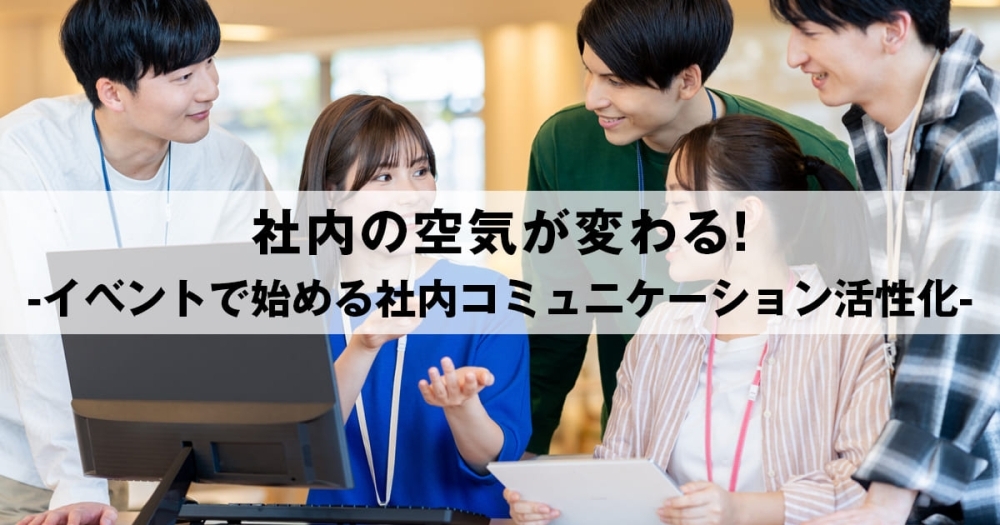
テレワークの普及により、多くの中小企業が社員同士のつながりが減っている課題に直面しています。従来の雑談や気軽な相談の機会が激減したことで、部門間だけでなく世代間の交流が減少しているのが現状です。
このような状況下において、最近では社内コミュニケーションを活性化する効果的な手段として「社内イベント」が注目を集めています。
そこでこの記事では、社内コミュニケーションが活性化しつながりが生まれるイベントの企画・運営方法を9つご紹介します。
【オンライン】社内コミュニケーションイベント4選
オンライン環境での社内イベントは、場所や時間の制約が少なく、比較的低コストで実施できる利点があります。
ここでは、社内コミュニケーションを活性化させる効果的な4つのオンラインイベントをご紹介します。
イベント①オンラインクイズ大会
1つ目は、オンラインクイズ大会です。オンラインクイズ大会は、Googleフォームなどの無料フォームツールを活用すれば、専門的な知識がなくてもすぐにクイズを作成できるので、比較的カンタンに実践することができるでしょう。
例えば、旭化成様の大阪支社では「大阪地区夏祭り」という伝統的な社内イベントの一環として、オンラインクイズ大会を開催しています。過去20回ほど開催されてきた恒例行事をコロナ禍でオンライン化する際に、従来のオフライン交流に代わる手段として導入されました。
実際には、チーム戦と個人戦の2つのブロックで構成され、自社に関する問題も盛り込むことで、社員の会社への理解を深める効果を実現しています。(※1)
このように、オフィスや自宅に関係なく全員が参加できるオンラインクイズ大会は、部署対抗戦といったチーム戦の形式を取ることで自然と会話が生まれるので、結束力につながるでしょう。
※1引用元:IKUSA「【開催事例】「オンラインクイズ大会」旭化成 大阪支社様」
イベント②バーチャル雑談カフェ
2つ目は、バーチャル雑談カフェです。バーチャル雑談カフェは、オンライン上の仮想空間にてアバターを介して雑談できるので、大人数での開催でもさまざまな人と交流することができます。
例えば、PR・広報領域で活動するライター・編集者のコミュニティ「トナリノ広報部」では、メンバー専用の「バーチャルカフェ」を開設しています。コロナ禍でオンラインイベントが乱立する中、「雑談はそもそも予定を入れてするものではない」という考えから、Gatherというバーチャルオフィスサービスを活用した自由度の高い交流スペースを提供しています。(※2)
このように、心理学的にも最適な人数設定により全員が発言しやすい環境が整うため、普段話す機会の少ない同僚との交流が自然に生まれ、組織内のコミュニケーション活性化につながります。
※2引用元:トナリノ広報部「オンラインでもさりげない交流を。メンバー専用「バーチャルカフェ 」をオープンした理由」
イベント③趣味共有会
3つ目は、趣味共有会です。個人の趣味や関心事を共有する発表型イベントでは、参加者が特別な準備をする必要がないため、参加ハードルが非常に低く実践しやすいイベントです。
例えば、とあるサービス業の企業では、隔月で「私の推し活」をテーマにした趣味共有会を開催しています。映画、読書、料理、旅行など各自が情熱を持って取り組んでいることを5分程度で発表することで、業務では見えない社員の多様な一面を知る機会になっているようです。
このように、社員の人間性や価値観を多角的に理解することで、職場での人間関係が豊かになり、相互尊重の風土を醸成する効果があります。
イベント④チーム対抗型オンライン謎解きゲーム
4つ目は、チーム対抗型のオンライン謎解きゲームです。市販の謎解きキットやオンライン専用ツールを活用した謎解きゲームでは、3~4名のチームで協力するため、自然と対話が活発になり実践しやすいイベントです。
例えば、従業員数150名以上のIT企業では、四半期に1回「謎解きチャレンジ」として、部署混合のチームで60分間の謎解きゲームを開催しています。普段接点の少ない開発部とマーケティング部のメンバーが同じチームになることで、異なる視点や発想を持つメンバー同士が協力し、多様性の価値を体験的に学んでいます。ゲーム終了後の振り返り時間では、各メンバーの貢献や考え方の違いを確認し合うため、実際の業務でのコミュニケーションに活かされます。
このように、ゲームの構造的にメンバーと協力する状況が設けられるため、強制的でない自然な会話とつながりが生まれるでしょう。
【オフライン】社内コミュニケーションイベント2選
次にご紹介するのは、オフラインでの社内イベントです。オンラインよりも表情や身振りを含む非言語コミュニケーションが生まれるので、より深い交流が生まれるようになります。
ここでは、オフラインで社内コミュニケーションを活性化する2つの社内イベントをご紹介します。
イベント⑤ランチシャッフル会
まずは、ランチシャッフル会です。異なる部署のメンバーでグループを編成してランチを行うため、業務とは一度離れたコミュニケーションとして自然体での交流がしやすいイベントになっています。
例えば、名刺管理サービスを展開するSansan株式会社では「Know Me」制度として、「他部署」で「過去に飲んだことがない」人と「3名まで」で飲みに行った場合、会社から一人につき3,000円を補助する制度を導入しています。(※3)
この制度により、普段接点の少ないメンバーと自然に交流ができるので、ヨコのつながりも重視した社内コミュニケーションが推進されます。また、参加者の自主性を尊重した「任意参加制」により、やらされ感がなく、自主的な交流としてより深いつながりが生まれます。
このように、ランチシャッフル会は、普段接点がないメンバーの人柄や仕事への価値観などを知るきっかけをつくれるため、組織全体のコミュニケーション活性化につながります。
※3引用元:UWORK「社内メンバーと飲むのが好きなあなたへ 他部署の人との飲みは3000円支給」
イベント⑥部署紹介プレゼン大会
次は、部署紹介プレゼン大会です。短い時間で各部署が持ち回りで業務内容や取り組みを紹介するイベントとして、部署間の連携強化や組織全体の活性化につながります。
例えば、サイボウズ株式会社では「仕事Bar」という制度を導入し、リラックスした雰囲気の中で真面目に仕事の話をする場を提供しています。5人以上の会が対象で、一人あたり1,500円を補助することで、業務上のコミュニケーションの質と量を高めています。(※4)
特に新しい人事制度の検討時には、のべ80名ほどの社員が参加し、制度の内容やあり方について活発な議論を展開。その後の開催報告も全社に公開することで、一方的ではなく社員一人ひとりが「自分ごと」として捉えられる仕組みを構築しています。
このように、発表準備の過程で部署内のコミュニケーションの活性化はもちろん、他部署の業務内容や取り組みを知ることができる点でも相互理解が深まり、自然な会話やつながりが期待できるでしょう。
※4引用元:サイボウズチームワーク総研「サイボウズ流「チームワークあふれる会社にするコミュニケーション」とは?」
【ハイブリッド】リモート・出社両方に対応する社内コミュニケーションイベント3選
ここまで、オンラインとオフラインに分けてご紹介してきましたが、近年はリモートワークとオフィス出社のハイブリッド型を採用する企業も少なくありません。
そこでここでは、リモートワークとオフィスのハイブリッド環境でも社内コミュニケーションを活性化できるイベントを3つご紹介します。
イベント⑦オンライン参加可能な懇親会
まずは、オンライン参加可能な懇親会です。オフィス出社組とリモート組が全員参加できるよう、社内にオンラインビデオの画面を投影したスクリーンを使うことで、同じ場所にいるかのように社内コミュニケーションを取ることができます。
例えば、四半期懇親会を現地30名・オンライン20名のハイブリッド形式で開催するのはどうでしょうか。現地の雰囲気を伝えるため複数のカメラをさまざまなアングルで設置したり、マイクをオンにしてリモート参加者がそれぞれ発言し会話ができる環境を構築できます。
特に効果的な取り組みとして、現地参加者がリモート参加者からのチャットメッセージを読み上げる「メッセージ紹介タイム」の導入です。しっかりとメッセージを紹介する時間を確保することで、リモート参加者が疎外感を感じることなく自然に交流ができるでしょう。
このように、参加形式を選べることでそれぞれの事情や好みに応じた参加が可能になり、現地参加者には対面ならではの濃密な交流を、リモート参加者には場所の制約を受けない便利さを提供できます。
イベント⑧オンライン社員総会&表彰式
次に、オンライン社員総会&表彰式です。全社員が業績を把握し、活躍した社員・チームを表彰する機会として、オンライン配信で開催することで、場所に関わらず全員が参加できるイベントです。
例えば、株式会社ビーズインターナショナルでは、「B's AWARDS2024」と題した社員総会・表彰式をベルサール渋谷ガーデンで開催し、272名が参加する大規模イベントを実施しています。「前期の業績を全社員が把握する」「好成績を収めた店舗、活躍した社員・チームを表彰する」「今期に向けて全社員が一丸となる機会にする」という目的のもと、イベントを2部制で構成しています。
特徴的だったのは、出張寿司職人による握り寿司提供やローストビーフカッティングなどのパフォーマンス演出です。そのパフォーマンスに、参加者から「おーー!」という歓声が上がり、社員のモチベーション向上や隣の人との会話が生まれる仕組みができます。
このように、オンライン社員総会や表彰式は、そのイベントを通じて社員への労いの気持ちを伝えることで、参加者同士の会話を弾ませる環境づくりに有効でしょう。
※5引用元:NEO DINING「出張寿司職人&ローストビーフカッティングで社員総会&表彰式のムードを上げる(株式会社ビーズインターナショナル様)」
イベント⑨サンクスカード・アプリ
最後は、サンクスカード・アプリです。感謝の気持ちを小さなカードに書いて相手に贈るサンクスカード制度、またはアプリ化したサンクスカードアプリは、社員間のつながりを高める制度として有効でしょう。
例えば、企業が導入するサンクスカード・アプリでは、社員同士が日常的に感謝の気持ちを送り合うよう制度かしています。「資料作成を手伝ってくれてありがとう」「丁寧な対応をしてくれてありがとう」といった具体的な感謝メッセージをアプリを通じて送ることで、お互いが「感謝されている」ことを強く実感できます。
特に効果的なのは、送られたサンクスカードが社内で見える化されることで、他の社員も良い行動を真似したくなる好循環が生まれることです。
このように、サンクスカード・アプリは、社内コミュニケーションが円滑になり、社員同士の仲がさらに良くなる効果も確認されていることから、組織全体にポジティブな雰囲気をもたらしてくれるでしょう。
失敗しない社内コミュニケーションイベント設計のコツ
これまでオンライン・オフライン・ハイブリッドの3つに分けて紹介した9種類のイベントですが、何の計画もなく実施しても社内コミュニケーションが生まれるとは限りません。
ここでは、失敗しない社内コミュニケーションのイベント設計方法についてコツを3つお伝えします。
コツ①よくある失敗パターンを事前に把握する
まずは、よくある失敗パターンを理解しておくことが重要です。こうしたイベントの実施には、社員の「やらされ感」による逆効果や、「一部だけ盛り上がり」といった格差、「マンネリ化・形骸化」による参加率低下など、共通する失敗要因が必ず生まれるからです。
例えば、テーマ設定が曖昧で目的が伝わらなかったり、特定の部署や役職だけが発言や参加しやすい雰囲気になっていたりすると、参加者の満足度は大きく低下します。
そのため、他社のイベント成功事例や、イベント企画に関する社員アンケートを参考にすることで、「誰が参加しても楽しめる構成になっているか」を確認することが重要です。
コツ②4つの基本原則を理解する
次に、社内イベントを成功させる基本原則を理解しましょう。その基本原則とは以下4つになります。
- 目的を明確にする
- 柔軟な参加形式を意識する
- 小規模から取り組む
- 開催後に振り返りの時間を設ける
目的の明確化では、「なぜこのイベントを開催するのか」「参加すればどんな良いことがあるのか」を具体的に言語化して、社員や上層部の理解と共感を得ることが出発点となります。
こうして目的を明確にしたことで、業務状況や個性の異なるさまざまな社員も参加しやすくなるイベント形式の前提がつくられます。柔軟性のある参加形式は、より多くの社員の参加が期待できるでしょう。
そしてイベント企画が固まってきたら、まずは小規模から取り組んでみてください。最初から完璧を求めず、少人数や短時間から始めて、参加者からのフィードバックを得ながら内容や規模を改善していきましょう。
イベントの企画や準備、運営を実施した後は、全体の振り返りとして意見交換の時間を設けることで、次回企画の際にその意見を取り入れて行う。このように、振り返りを行いながら段階的に改善する意識を持つことが重要です。
以上が、社内イベントを成功させる4つの基本原則です。
コツ③心理面に配慮して企画する
3つ目は、社員の心理面に配慮して企画することです。人は誰かに行動を強制されると反発心を抱きやすい心理面から、仮に強制参加させても受け身な姿勢になり、ストレスを感じやすくなってしまうからです。
重要なのは、強制参加ではなく「参加したくなる」魅力や価値を明確に伝えることです。参加者にとってのメリットを明示することで、社員が自ら参加したいと感じる環境を整えます。
そのためには、企画段階で社員から意見をもらったり、当日参加または事後の感想を共有してもらうことで、異なる性格をもつさまざまな社員の心理に配慮した企画にすることで「その企画なら参加したい!」と思ってもらえる内容にブラッシュアップできるでしょう。
【よくある質問】社内コミュニケーションのイベントについて
実際の導入現場では具体的で実践的な疑問が数多く生じることになります。予算設定への不安、参加形式の決定基準、効果測定の具体的手法、運営負荷の軽減策など、理論を理解していても現場特有の課題に直面するケースは少なくありません。
ここでは、社内コミュニケーションのイベントに関する導入・運営において最も頻繁に寄せられる質問について、実践的な視点から詳しく解説していきます。
質問①実施費用はどのくらいかかりますか?
社内コミュニケーションイベントの実施費用は、月1回開催の場合で無料から3万円程度が現実的な範囲と考えられます。オンライン中心のイベントであればZoomやGoogleフォームなどの無料ツールを活用することで、追加コストをほぼゼロに抑えることができるでしょう。
ほかにも、バーチャル雑談カフェやオンラインクイズ大会であれば、準備時間も含めて最も費用効率が良く、外部講師の招聘や専用会場の確保が必要な場合でも5万円から10万円程度の予算で実現できます。
ただし、高額な一回限りのイベントよりも少額でも定期的に継続できるイベントの方が長期的には大きな効果を生み出すため、継続性を重視した予算設定が重要です。費用対効果を考える際は、新卒採用に100万円以上、中途採用に数十万円のコストがかかることを考慮すると、月数万円の投資で離職率を改善できれば十分にペイする計算になります。
質問②参加は任意にすべきか必須にすべきか?
参加形式については基本的に任意参加を推奨します。なぜなら、強制参加は逆効果のリスクが高く、参加者が受動的になったりイベント自体への反感を招いたりする可能性があるからです。
効果的なアプローチとしては、目的と意義の丁寧な説明により自然な参加意欲を促進することです。「なぜこのイベントが必要なのか」「参加することでどんなメリットが得られるのか」を具体的に説明することで社員の理解と共感を得られます。
また、参加しない社員へのフォローも重要な要素です。不参加者を責めるのではなく、イベントの様子を後日共有したり、次回参加への自然な誘導を行ったりする配慮が必要です。業務時間内での開催の場合は事前調整と代替案の検討が必要になり、どうしても参加できない社員には別の参加方法を提供したり録画配信で後日視聴できるようにしたりするなど公平性を保つ工夫をおこないましょう。
質問③効果測定はどのように行えばよいですか?
効果測定や評価は、短期・中長期の時間軸を意識して実施することが重要です。なぜなら、感覚的な評価だけでは施策の効果を定量的に把握できず、上層部への説明責任も果たせないからです。
具体的な測定手法として、まず参加者アンケートにより満足度と改善提案、次回参加意向を調査し、単なる満足度だけでなく具体的にどの部分が良かったか、何を改善すべきかを詳しく聞き出すことで次回への具体的な改善につなげられます。
中期的には、社内コミュニケーション頻度の観察・ヒアリングにより、部署間の相談件数や非公式な交流の増加、協力事例の発生など定性的な変化を定期的に記録していきます。さらに、離職率やエンゲージメントサーベイの結果を活用し、少なくとも3ヶ月から半年程度のスパンで変化を追跡することも有効でしょう。
【まとめ】イベントを強い組織づくりへの第一歩に
本記事では、社内コミュニケーション活性化の取り組みとして、9種類の実践的社内なイベントと、その効果的なコツについて詳しく解説してきました。社内イベントは単なる親睦活動ではなく、社員間のつながりを深めて組織力を向上させるための投資として位置づけることが重要です。
最初から大規模なイベントを企画するのではなく、少人数でのランチシャッフル会やオンラインクイズ大会など、社員の反応を見ながら内容や規模を調整していくことで、組織の実態にあったイベント形式を見つけることから始めてみてはいかがでしょうか。
社内コミュニケーションの活性化として今回ご紹介したイベントが、組織づくりへの第一歩として少しでもお役に立てれば幸いです。




![onemind[離職率の低下に繋がる!] 社員情報・企業理念・感謝文化・社内報・出退勤管理(※オプションで追加可能)・社内文書](/img/ownedmedia/about_img01_pc.png)